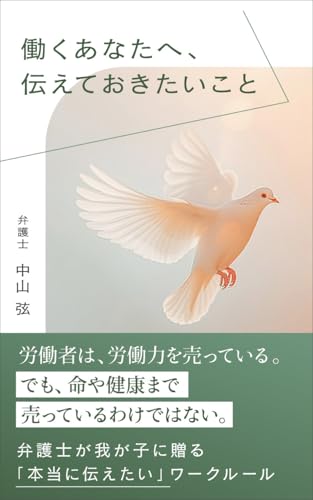「突然、解雇を言い渡された」
「会社から一方的に辞めるよう言われたが納得がいかない」
そんなとき、まず知っておきたいのは、解雇が法的に有効かどうかの判断基準です。
本記事では、労働契約法16条に基づく「客観的合理的理由」と「社会的相当性」という2つの要件を中心に、どんな場合に解雇が無効とされるのかを裁判例も踏まえて分かりやすく解説します。
なお、「辞めてくれ」と言われただけの場合など、解雇か自己都合退職かで争いになるケースもあります。どんな場合に解雇と言えるのか、注意すべき点は何かについては、口頭で「辞めろ」と言われたら解雇?自己都合?|境界の判断ポイントと裁判例で解説しています。
また、雇用期間が定められている労働者について、期間満了時に契約を終了させることを「雇止め」と言いますが、これが許される判断基準については、雇い止めはどのような時に許されるかで解説しています。
懲戒解雇・整理解雇・普通解雇の違い
「解雇」と一口に言っても、その内容や法的な性質はさまざまです。
解雇の種類によって、どのような場合に有効とされるかの基準も異なります。
現在あなたが受けた解雇がどの種類に当たるのかを押さえることが、対応を考えるうえでの第一歩になります。
懲戒解雇
まず、会社の労働者に対する制裁、つまり「罰」として行われる「懲戒解雇」があります。
懲戒解雇は、「罰」として行われるという特質から、これが許されるための条件は特に厳しく制約されます。
懲戒解雇が許される基準について詳しくは、懲戒解雇されそうなときに知っておきたい法律知識と今すぐできる対処法で解説しています。
整理解雇
次に、経営難による人員削減などのもっぱら会社側の事情で行われる「整理解雇」があります。
整理解雇は、労働者側の事情ではなく、会社側の事情で行われるという特質から、やはりこれが許されるための条件は厳しく判断されます。
一般的に、「人員削減の必要性」「解雇回避努力」「人選の合理性」「手続の妥当性」といった4要件が考慮されます。
普通解雇
最後に、上で挙げた「懲戒解雇」や「整理解雇」以外の解雇を、一般に「普通解雇」と言います。典型的には、能力不足や適格性欠如を理由とする解雇があります。
以下では、この普通解雇および整理解雇を中心に、どのような場合に解雇が有効とされ、逆に無効と判断されるのかを詳しく見ていきます。
懲戒解雇については、懲戒解雇されそうなときに知っておきたい法律知識と今すぐできる対処法をご覧ください。
また、試用期間に行われる本採用拒否も解雇の一種ですが、これがどのような時に許されるのかについては本採用拒否・試用期間中の解雇は有効?裁判例でわかる判断ポイントで解説しています。
許される解雇理由とは?
解雇は法的にどう判断される?労働契約法16条とは
解雇に関するもっとも重要な法律条項といえば、労働契約法16条です。
労働契約法16条は
解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする
と規定しています。
仕事を失うということは、働く人にとっては極めて重大な打撃となります。
そこで、労働者を保護する観点から、裁判例上、解雇について「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が要求されるようになりました。労働契約法16条は、このような裁判例を通じて形成されてきた考え方を、そのまま取り入れて作られた条項です。
客観的合理的理由と社会的相当性
まず、解雇が正当となるためには、「客観的合理的理由」が必要であり、さらに「社会通念上相当」と認められる必要があります。
「客観的合理的理由」や「社会通念上相当であること」の具体的な意味については、この後詳しく説明しますが、まずは「会社は労働者を自由に解雇できるわけではない」ことを頭に入れて頂ければと思います。
なお、期間の定めのある雇用契約の場合に、期間途中で労働者を解雇するには、さらに厳格な「やむを得ない事由」が必要となります。この点について詳しくは、契約社員の期間途中の解雇は有効?|「やむを得ない事由」と裁判例で見る判断基準で解説しています。
派遣社員の場合も同様に、期間途中の解雇には「やむを得ない事由」が必要です。よく問題となるのが、労働者派遣契約が中途解約された場合に「やむを得ない事由」に該当するのかですが、この点については、派遣社員の解雇は許される?|派遣元・派遣先の関係と「やむを得ない事由」を裁判例で解説で解説しています。
解雇が無効となること
もう一つ重要なのは、客観的合理的理由や社会通念上の相当性を欠く場合、解雇は法律上無効とされる点です。
この場合、会社が解雇を通告しても法的な効力は生じず、労働者の地位はそのまま存続します。
そのため、解雇をめぐる争いでは、労働者は雇用関係が続いていること(地位の確認)と、職場復帰までの賃金の全額支払いを求めるのが基本的な主張となります。
このような解雇を争う場合の主張内容について詳しくは、不当解雇で慰謝料は請求できる?職場復帰が基本/認められるケースと否定例で解説しています。
具体的にどのような場合に解雇が無効となるのか
問題は、どのような場合に「客観的合理的理由」や「社会的相当性」があるといえるのか?という点です。
ここでは、客観的合理的理由と社会的相当性の有無について判断する際の、いくつかの視点について説明していきます。
なお、解雇の有効性が争われた具体的な事例を知りたいという方のために、近年の解雇裁判例を、解雇の種類や理由などから検索できるようにしています(⇒裁判例から学ぶ解雇基準)。ご自身の状況に近い事例を探して、今後の対応や判断の参考にして頂ければと思います。
解雇の効力が否定された最高裁判例|高知放送事件
「客観的合理的理由」と「社会的相当性」の問題を論じるときに必ず取り上げられるとても有名な判例として、「高知放送事件判決」という最高裁判決があります。
これは、宿直のアナウンサーが、寝過してラジオのニュース放送に穴をあけるという事故を2週間に二度(!)起こしたために解雇された事案です。
この事案で最高裁は
- 悪意や故意がないこと
- 放送空白時間の短さ
- 謝罪の意の表明
- ともに寝過した記者に対する処分が軽いものにとどまっていること
- 会社側の事故防止対策の不備
- 本人に過去に事故歴がないこと
等々の事情を考慮して、解雇を無効と判断しました。
ニュースに穴をあける大ミスを短期間で二度も行ったと聞くと、一般の方の感覚からすると、ひょっとすると「クビやむなし!」と思われるかもしれませんが、裁判所はかなり厳格な判断をしているのです。
裁判所がどこを見ているか?合理性・相当性のチェックポイント
この高知放送事件を含め、これまで数多くの裁判例で示されてきた客観的合理的理由や社会的相当性の判断基準について、例えば、ある裁判例(平成29年10月18日東京高裁判決)は、次のように整理しています。
解雇事由の客観的合理性は、解雇事由の程度やその反復継続性のほか、当該労働者に改善や是正の余地があるか、雇用契約の継続が困難か否か等について、過去の義務違反行為の態様や、これに対する労働者自身の対応等を総合的に勘案し、客観的な見地からこれを判断すべきであり、解雇の社会的相当性は、客観的に合理的な解雇事由があることを前提として、本人の情状や使用者側の対応等に照らして解雇が過酷に失するか否かという見地からこれを判断すべきである。
段階を踏まずに即解雇は許されない?指導・改善措置の有無
このうち、当該労働者に改善や是正の余地があるかという点についていえば、能力や適格性が欠如していることを理由として解雇された場合、裁判所が強く着目する点の一つに、解雇に至るまでにとられた改善・教育措置の内容があります。
解雇が労働者にとって大きな不利益をもたらすものであることに照らすと、解雇を回避するために何の措置も取らずに(段階を経ずに)いきなり解雇するということは基本的に許されないという発想が強いといえます。
このような能力不足や成績不良を理由とする解雇の判断基準については、能力不足・勤務成績不良を理由にした解雇は有効?無効?|裁判例でわかる判断基準で詳しく解説しています。
病気で働けない場合の解雇
病気で働けないことによる解雇というのも典型的な解雇の場面の一つです。
多くの会社では、病気による欠勤が長期に及ぶ場合には、一定期間を休職とし、休職期間満了時に復職できない場合には自然退職や解雇となる制度を設けています。
そのため、休職期間満了時の解雇という形で問題となる場合が多いのですが、このときに注意が必要なのは、復職できるかどうかの判断にあたっては、必ずしも、休職前に従事していた仕事に復職できる必要がある訳ではないという点です。
つまり、他の業種への配転の現実的可能性があるにもかかわらず、その配転について検討しないまま、復職不可と判断して休職期間満了とともに解雇することは許されないのです。
休職期間満了時の解雇の問題について詳しくは、休職期間満了時の解雇が許されるかで解説しています。
整理解雇が認められるには?裁判例で見る4つの要件
経営不振による人員削減・部門の廃止など、経営上の必要性を理由に解雇を行う整理解雇については、数々の裁判例を通じて、有効となるための要件として、以下の4つの要件が確立しています。
- 人員整理の必要性が存在すること
- 解雇を回避するための努力が尽くされていること
- 被解雇者の選定が客観的合理的な基準によってなされたこと
- 労働組合または労働者に対して事前に説明し、納得を得るよう誠実に協議を行ったこと
こうした要件を満たしていないという場合には、整理解雇は無効となります。
整理解雇は、成績不良による解雇のように働く人に責任があって行われるものではなく、もっぱら会社側の事情で行われるものです。
したがって、その判断はより厳格に行われる必要があります。
なお、事業所や支店の閉鎖に伴う解雇の場合も、整理解雇として扱われ、同様に4要件が適用されます。
4要件が実際の裁判例において具体的にどのように判断されるのかについては、パート従業員に対する整理解雇が無効とされた裁判例|解雇が認められない理由で解説しています。
法律で禁止されている解雇理由とは?
このように労働契約法16条によって、客観的合理的理由あるいは社会通念上の相当性のない解雇は無効となりますが、それとは別に、解雇が許されない場合を個別に定めている法律の規定もあります。
これらに該当する場合には、「客観的合理的理由」や「社会的相当性」を持ち出すまでもなく、解雇は無効ということになります。
少し細かくなりますが、いくつか具体例を見てみます。
・国籍、信条、または社会的身分に基づく差別的解雇は許されません(労働基準法3条)。
・労働者が、労働基準法違反の事実を労働基準監督署等に申告をしたことを理由とする解雇も許されません(労働基準法104条2項)。
・労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇も禁止されています(労働組合法7条1項)。
・女性労働者については、婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業の請求取得を理由とする解雇は許されません(雇用機会均等法9条3項)。
・妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は原則無効とされ、使用者の側が婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇でないことを証明しなければならないとされています(雇用機会均等法9条4項)。
・労災で休業している期間及びその後30日間も解雇が許されません。(詳しくはこちら⇒労災で休業中に解雇は許されるか)
・公益通報を行ったことを理由とする解雇も許されません。(詳しくはこちら⇒内部告発を理由に解雇は許される?公益通報者保護法と裁判例で解説)
個別の制約規定に該当する場合
もっとも、実際に、使用者が解雇をしようとする時に、例えば「あなたは労働組合に加入したから解雇する」「あなたは労働基準監督署に労基法違反の事実を申告をしたから解雇する」などと法律上禁じられた事由を正面から解雇理由にすることは普通は考えられません。
しかし、建前上もっともらしい解雇理由が掲げられていても、本当の理由は別にあることを明らかにして解雇の無効を主張することができます。
解雇予告と解雇予告手当のルール
ここまで説明してきた「解雇理由」の問題とは別に、あわせて「手続き」面にも守るべきルールがあります。
代表的なものが「30日前の解雇予告」または「解雇予告手当の支払い」です。
解雇予告や予告手当の意味や、必要となる場合について詳しくは解雇予告・解雇予告手当とは?|必要な場面・例外・計算方法・請求手順で解説しています。
解雇されたときの対応方法|まず何をすべきか?
不当な解雇に対しては、その後、どのように行動するかが重要になってきます。
不用意な行動が後々不利に働くこともありますので、慎重な対応が必要です。
以下では、解雇された直後に特に重要となる3つの対応を紹介します。
解雇理由証明書の交付請求
まず、真っ先にすべきなのは、解雇理由証明書(労働基準法22条1項)の交付請求です。
解雇理由証明書を交付させることによって、解雇理由が明確になり、解雇の効力を争う余地があるのかどうかの判断が可能となります。また、解雇理由証明書を早い段階で出させることによって解雇理由の後付けを防ぐという意味もあります。
解雇理由証明書について詳しくは解雇理由証明書とは?|請求方法ともらえないときの対応を解説で解説しています。
退職を前提とした行動をとらないこと
退職届の提出や退職金の請求など、退職を前提とするような行動をとらないことも大切です。
その他、解雇直後の行動の注意点については、解雇通知を受けたら?すぐに取るべき行動と注意点で解説しています。
速やかに相談
解雇理由証明書を手に入れたら、速やかに弁護士のところに相談に行きましょう。
不当解雇の相談先としては、労働基準監督署や労働組合もあります。不当解雇の相談先と相談する際に気をつけたいことについては、不当解雇されたらどこに相談すべき?労基署・弁護士・労組の比較と注意点で解説しています。
不当な解雇でお困りの方へ
不当な解雇に対してどう対応すべきかは、具体的な事情によっても変わってきます。ご自身の状況に照らして、今何をすべきかを知りたい方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
⇒労働相談@名古屋の詳細を見てみる
次に読むと理解が深まる記事
- 解雇時によく問題となる退職金について解説しています。
⇒解雇・懲戒解雇時の退職金の不支給・減額は有効?|裁判例で見る判断基準 - 能力不足や成績不良を理由とする解雇が許される場合について裁判例をもとに解説しています。
⇒能力不足・勤務成績不良を理由にした解雇は有効?無効?|裁判例でわかる判断基準 - 不当な解雇をされたときに知っておきたいポイントを体系的に整理した総合ガイドです。
⇒不当解雇トラブル完全ガイド|判断基準・対処法・相談先まとめ
解雇の効力が争われた具体的な事例を知りたい方へ
実際の裁判例でどのような判断がされているのかを知りたいという方のために、近年の解雇裁判例を解雇理由、解雇の種類、判決結果から検索できるようにしました。
ご自分のケースに近いものを探して、参考にして頂ければと思います。
⇒解雇裁判例を見てみる