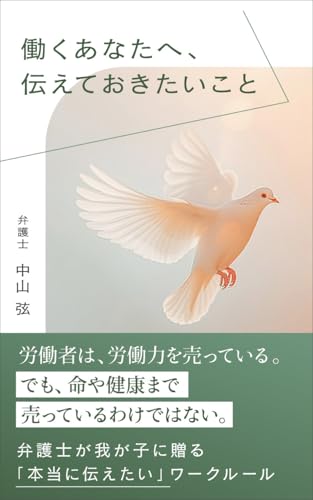Q1 競業避止義務とは何ですか?
競業避止義務とは、使用者の事業と競合する事業を営んだり、競合する会社に就職するなどの競業行為によって使用者の利益を害さないようにする義務のことをいいます。
Q2 労働者は在職中に競業避止義務を負いますか?
労働者は、在職中、使用者の正当な利益を信頼関係を破壊するような不当な態様で侵害してはならないという「誠実義務」を負っています。その誠実義務の一つとして、特別な合意がなくとも、在職中には競業避止義務を負います。
Q3 退職後も競業避止義務を負うのですか?
雇用関係が終了していることから、退職後には競業避止義務は負わないのが原則です。ただし、退職時に競業避止義務を定めた誓約書に署名するなど、特別な合意や就業規則の定めがある場合には、その範囲で競業避止義務を負うことがあります。
Q4 競業避止の誓約書にサインをしたら、常に退職後も競業避止義務を負うのですか?
退職後の競業行為を制約する合意は、職業選択の自由や営業の自由を強く制約します。そのため、合意があれば常に有効となるわけではなく、職業選択の自由、営業の自由を不当に制約する不合理な内容であれば無効となり、競業避止義務も負いません。
Q5 退職後の競業避止義務を定めた合意の有効性は、どのように判断されるのですか?
使用者に保護すべき正当な利益があるのか、労働者が競業避止を必要とする地位にいたのか、制約の手段(期間や地理的範囲、制約対象行為など)に合理性があるのか、代償措置の有無などを総合的に考慮して判断されます。
Q6 代償措置とはなんでしょうか?
退職後の競業行為を禁ずる合意は、労働者の職業選択の自由、営業の自由を強く制約します。そのため、合意の有効性を判断するにあたっては、そのような制約に見合った経済的な補償が行なわれているか否かが、重要な判断要素の一つとなります。この経済的補償のことを「代償措置」といいます。
Q7 競業避止義務の合意が有効である場合に、これに違反するとどうなりますか?
損害賠償請求や競業行為の差し止めが考えられます。
損害の範囲については、競業行為と相当因果関係がある損害かが大きな問題となります。
合意書の中で、合意に違反した場合の違約金額が定められている場合も、当然にその金額の請求が許されるわけではありません。賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反にならないかや、不相当に過大なものとして無効とならないかといった点が問題となります。
▼競業避止の誓約書が有効と認められた裁判例
▼競業避止義務違反による退職金の返還請求が否定された裁判例
Q8 退職にあたり競業避止の誓約書へのサインを求められていますが、サインをしなければいけませんか?
誓約書にサインをしなければならない義務はありませんので、拒否しても構いません。誓約書にサインしないことを理由に「退職を認めない」ことも許されませんし、退職金の不払いを正当化する理由にもなりません。
Q9 誓約書へのサインを拒否したいのですが、どのように言えば良いでしょうか?
①余分なことは言わずに単に「この内容に合意はできません」と伝える。
②会社に迷惑をかけるつもりはないことを伝えつつ、「あまりに制約範囲が広すぎるので応じられません」と伝える。
③合意できない条項が一部であれば、「○○条は合意出来ません」と付記して提出する。
といった方法などが考えられます。
Q10 誓約書にサインをしなければ、退職後の行動には何も制約を受けないのですか?
退職後の競業避止義務を定めた合意や就業規則の定めがない場合でも、不正競争防止法や民法の一般原則(不法行為)による規制を受けます。
したがって、何らの制約も受けないわけではありません。
Q11 不正競争防止法による制約とはどういう意味ですか?
不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争等を確保する」ことを目的とする法律で、「営業秘密」の不正な使用や開示について、差止請求や損害賠償請求を認めています。
もっとも、ここで保護される「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」という3つの要件を満たすことが必要です。
Q12 退職後に前の会社の顧客と取り引きをする行為が民法上の不法行為となる場合がありますか?
前の会社の顧客との間で取引を行うことも自由競争として許されるのが原則です。したがって、前の会社の顧客と取り引きをすること自体は違法とは言えません。
ただし、自由競争の範囲を逸脱するような方法で行われる場合には、違法な行為として損害賠償義務を負うことがあり得ます。
例えば、前の会社について虚偽の事実を述べて信用をおとしめたり、前の会社の重要な秘密を用いて顧客を奪うような場合です。
Q13 退職後に備えて、在職中に同業の会社を設立する行為は違法ですか?
退職後に備えて在職中から一定の開業準備をすること自体は必要な行為ですので、単に同業他社を設立しただけで直ちに誠実義務に違反するとは言いがたいと考えられます。
ただし、在職中に営業行為を開始するなど実際に競合行為を行った場合には誠実義務違反となる点に注意が必要です。
Q14 同業他社に転職する際に、他の従業員を勧誘することは違法ですか?
他の従業員にも職業選択の自由(転職する自由)があることからすると、勧誘をすること自体が違法となるとは言えません。
もっとも、例えば虚偽の事実や会社の信用をおとしめるような事実を告げたり、地位を利用して勧誘を繰り返すなど、著しく背信的な方法で行われ、社会的相当性を逸脱した場合には違法となります。
Q15 元の会社から「競業避止義務に違反している」という通知を受けました。どのように対処すれば良いですか?
相手が何を根拠に主張をしているのか(誓約書なのか就業規則なのか等)をよく確認しましょう。慌てて相手と接触して不必要な情報を与えないことも大切です。必要な資料や情報を整理した上で、早めに弁護士に法的判断を仰ぐことをお奨めします。
▼「競業避止義務に違反している」と言われたら?元の会社から警告を受けたときの正しい対応法
さらに詳しく知りたい方は・・・
競業避止義務・秘密保持義務についてさらに詳しく知りたい方は、退職・転職で気をつけたい競業避止義務と秘密保持義務【まとめ】を、ご覧ください。