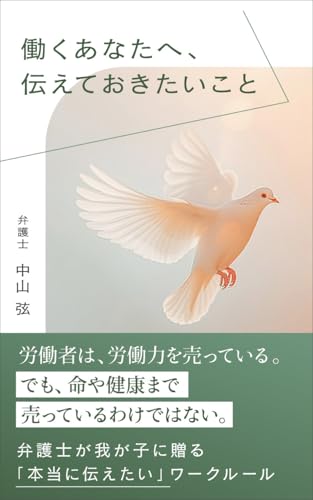退職後、元の勤務先から「営業秘密を漏洩したのではないか」として責任を追及される――。
そんな思いがけないトラブルに巻き込まれたとき、会社側が根拠として持ち出してくることがあるのが「不正競争防止法」です。
不正競争防止法は、あまり聞き慣れない法律かもしれませんが、「事業者間の公正な競争を確保する」ことを目的とし、特定の不正な行為に対して差止請求や損害賠償を認めている法律です。
そのため、元従業員(あるいは元役員)と会社のあいだで秘密保持や競業避止を巡って紛争になった際に、「あなたの行為は不正競争防止法に違反している」として、責任追及の根拠とされることがあります。
もっとも、不正競争防止法で保護される営業秘密に該当するためには、一定の厳格な条件を満たしている必要があります。
本記事では、「不正競争防止法における営業秘密とは何か」「法律上、どのような条件が求められるのか」を実際の裁判例をもとにわかりやすく解説します。
なお、不正競争防止法とは別に、秘密保持の誓約書で秘密保持が義務付けられた「営業秘密」の意味について問題となる場合があります。このようなケースについてはこちらで解説していますのでご覧ください。
⇒秘密保持誓約書と秘密の意味
不正競争防止法における「営業秘密」とは|定義と3つの要件
「営業秘密」と聞くと、企業にとって大切な情報、といった漠然としたイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、不正競争防止法における「営業秘密」は厳密に定義されおり、これによって保護されるためには3つの要件を満たす必要があります。
不正競争防止法第2条6項では、営業秘密について、次のように定義しています。
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
つまり、営業秘密に該当するためには、次の3つの要件を満たすことが必要ということになります。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
実務上、特に争点となりやすいのは「秘密として管理されているかどうか」です。
そこで、この「秘密管理性」について、実際の裁判例をもとに詳しく見ていきましょう。
なお有用性の問題については、こちらで解説しています。
⇒不正競争防止法における「営業秘密」とは?裁判例にみる有用性のポイントを弁護士が解説
秘密として管理されているか
秘密管理性が否定された裁判例①(東京地裁平成20年11月26日判決)
この事案では、インターネットでCDやレコードなどを販売していた会社が、退職して競業会社に就職した元従業員とその身元保証人に対して、商品の仕入先情報の漏洩を理由に損害賠償を求めました。
争点となったのは、商品の仕入れ先情報が不正競争防止法における「営業秘密」に該当するかです。
秘密管理性が求められる理由
裁判所は、まず、営業秘密に該当するために「秘密として管理されていること」が求められる理由について次のように説明しています。
- 営業秘密は、情報という無形なものであって,公示になじまない
- そのため、保護されるべき情報とそうでない情報とが明確に区別されていなければ、その取得、使用又は開示を行おうとする者にとって、当該行為が不正であるのか否かを知り得ず,それが差止め等の対象となり得るのかについての予測可能性が損なわれる
- (その結果)情報の自由な利用、ひいては、経済活動の安定性が阻害されるおそれがある
要するに、開示が許されない情報と分かるようにしておかないと、何を開示していいかの判断ができなくなって、情報の自由な利用が出来なくなってしまう、ということです。
秘密管理性の判断基準
そして、裁判所は、このような趣旨に照らすと、当該情報を利用しようとする者から容易に認識可能な程度に、保護されるべき情報である客体の範囲及び当該情報へのアクセスが許された主体の範囲が客観的に明確化されていることが重要とした上で、秘密として管理されているかどうかの主な判断要素として、次の点を挙げました。
- 当該情報にアクセスした者に当該情報営業秘密であると認識できるようにされているか
- 当該情報にアクセスできる者が制限されているか
さらに、その判断にあたっては、以下の点を考慮すべきとしています。
- ・当該情報の性質
- ・保有形態
- ・情報を保有する企業等の規模
- ・情報を利用しようとする者が誰であるか
- ・従業者であるか外部者であるか
秘密管理性の否定
本件では、以下の点を指摘して、秘密管理性は認められない、と結論づけました。
- ・原告においては、アルバイトを含め従業員でありさえすれば,ユーザーIDとパスワードを使って、本件仕入先情報が記載されたファイルを閲覧することが可能であったこと
- ・ファイル自体には、情報漏洩を防ぐための保護手段が講じられていなかったこと
- ・従業員との間で締結した秘密保持契約も、その対象が抽象的で、本件仕入先情報が含まれることの明示がされていなかったこと
- ・従業員に対して、本件仕入先情報が営業秘密に当たることについて,注意喚起をするための特段の措置も講じられていなかったこと
- ・本件仕入先情報が、その性質上,秘匿性が明白なものとはいい難く、原告の従業員にとって,それが外部に漏らすことの許されない営業秘密であるということを容易に認識できるような状況にあったとはいえないこと/li>
秘密管理性が否定された裁判例②(平成23年9月29日東京地裁判決)
この事案は、健康器具を販売する会社で取締役兼営業担当部長であった者が、退社後に入社した競業会社に対して顧客名簿を開示した行為等が問題となったケースです。
顧客名簿に記載された顧客情報が、不正競争防止法における「営業秘密」にあたるのかが争われました。
秘密管理性の否定
裁判所は、まず秘密として管理されているというためには、次の点が重要と述べました。
ある情報が秘密として管理されているというためには、当該情報に接し得る者が制限され、当該情報に接した者に当該情報が秘密であると認識し得るようにしていることが必要である
その上で、次の点を指摘して、本件各名簿に記載された顧客情報は、秘密として管理されていたとはいえないと結論づけました。
- ・顧客情報の閲覧や印刷に原告代表者の事前の承認や許可を得るという秘密管理規定で定められた手続が、実際には遵守されていなかったこと
- ・パスワードの設定等による物理的な障害も設けられていなかったため,権限のない原告従業員でも自由に閲覧したり印刷したりすることができたこと
判断のポイント
この判決でも重視されていますが、形式上のルールでは閲覧等が制約されていても、実際にはそれが守られておらず、物理的にもそれが制約されていないという場合は、秘密として管理されていたとはいえないことになります。
秘密管理性が否定された裁判例③(平成22年10月21日大阪地裁判決)
この事案は、主に投資用マンションの販売を行っている不動産会社が、退職した元従業員らが競合他社に顧客情報を開示したとして、損害賠償などを求めたケースです。
争点として、元従業員らが使用した顧客情報が営業秘密に該当するかどうか、特に「秘密として管理されていた」といえるかが問題となりました。
顧客情報の性質
まず、裁判所は、本件顧客情報の特質について次の点を指摘しました。
- 従業員が日々の営業活動において取得して会社に提供することにより会社が保有し蓄積する顧客情報となるものも含まれていること
- 顧客情報を利用した営業活動においては、従業員が特定の顧客との関係で個人的な親交を深め、その関係が会社を離れた個人的な交際関係も同然となる場合も生じ得ること
したがって、退職従業員にその自由な使用を禁ずるためには、日々の営業の場面で,上記顧客情報が「営業秘密」であると従業員らにとって明確に認識できるような形で管理されていなければならず、その点は、実態に即してより慎重に検討される必要があるとしました。
秘密管理性が否定された理由
その上で、裁判所は以下の点を挙げて、当該顧客情報が「秘密として管理されていた」とは認められないと結論づけました。
- 顧客情報ファイルの引き継ぎに際して、特別な注意が与えられるとか、管理に関する特別な指示がされるなどの特別の手当がされていなかったこと
- 従業員の秘密保持の誓約書の提出も徹底されていたとはいえないこと
- そうすると、会社は秘密保持義務が不徹底のまま契約者台帳ファイルの管理を個々の営業部従業員に任せていたというべきであること
- 営業部従業員は、必要に応じて契約者台帳のコピーをとって社外に持ち出すなどしており、契約者台帳ファイルの管理は会社の手もとを離れてしまっていたと言わざるを得ないこと
判断のポイント
業界によっては、顧客と営業社員との関係は会社を離れた個人的な関係に発展し継続していくこともあり、退職後の秘密保持や競業行為が問題となる場面では、こうした観点も十分に考慮される必要があります。
この点を踏まえ、本件では、秘密管理性について、実際の管理実態を踏まえた慎重な判断がなされています。
秘密管理性が肯定された裁判例(平成26年4月17日東京地裁判決)
ここまでは、秘密管理性が否定された裁判例を紹介してきましたが、秘密管理性が認められた例も見てみます。
この事案は、モデルやタレントのマネジメント業を行う会社が、退職後、同業の会社を立ち上げた元従業員に対して、同社の登録モデルに関する個人情報を使用したとして損害賠償を求めたものです。
登録モデルの個人情報が、不正競争防止法における「営業秘密」に当たるのかが争われ、その秘密管理性の有無が問題となりました。
秘密管理性が認められた理由
裁判所は、次の点を指摘し、秘密管理性を肯定しました。
- 登録モデル情報は、外部のアクセスから保護された原告の社内共有サーバー内のデータベースとして管理され、その入力は、原則として、システム管理を担当する従業員1名に限定し、これへのアクセスは、マネージャー業務を担当する従業員9名に限定して,その際にはオートログアウト機能のあるログイン操作を必要としていたこと
- 登録モデル情報を印刷した場合でも,利用が終わり次第シュレッダーにより裁断していること
- 会社は就業規則で秘密保持義務を規定しており、モデルやタレントのマネジメント及び管理等という業務内容に照らせば、登録モデル情報について,上記のような取扱いにより、従業員に登録モデル情報が秘密であると容易に認識することができるようにしていたといえること
元従業員の反論と裁判所の判断
元従業員らは、他の従業員も登録モデル情報を入力することがあったことなども主張しました。
しかし、裁判所は、「他の従業員による登録モデル情報の入力が恒常的に行われていたと認めることはできない」として、この主張を退けました。
つまり、他の従業員が登録モデル情報を入力することが一部あったとしても、秘密管理性の評価を覆すには足りないとしたのです。
判断のポイント
この事案からは、秘密管理性が肯定されるためにとられるべき情報管理のあり方が読み取れます。
・誰が情報にアクセスできるのか
・情報の扱いが社内でどれだけ明確にされているか
・実態としての管理のあり方
に照らして、実質的な判断がなされていることが分かります。
上でとりあげた秘密管理性を否定した裁判例②では、秘密管理規定で定められた手続が実際には遵守されていなかったことや、パスワードの設定等が行われていなかったことと対比して頂ければと思います。
まとめ
以上の事例から、不正競争防止法における営業秘密として保護されるためには、情報の性質や保有形態など様々な観点から、秘密管理性が厳格に求められることがお分かり頂けるかと思います。
さらに、営業秘密として認められるためには、「秘密として管理されていること」だけでなく、「有用性」や「非公知性」といった他の要件も満たす必要があります。
「有用性」については、こちらで解説していますので、ご覧ください。
⇒不正競争防止法における「営業秘密」とは?裁判例にみる有用性のポイントを弁護士が解説
あわせて読むと理解が深まる記事
秘密保持誓約書に記載された「営業秘密」の意味については、別に考える必要があります。
⇒秘密保持誓約書と秘密の意味
退職後の秘密保持義務の有効性や限界について、裁判例をもとに解説しています。
⇒退職後も秘密保持義務は続く?裁判例にみる合意の効力とその限界
競業避止義務・秘密保持義務全般について、さらに詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事からご覧ください。
⇒退職・転職で気をつけたい競業避止義務と秘密保持義務【まとめ】
不正競争防止法や秘密保持に関してお困りの方へ
秘密保持に関する判断は、具体的な事情によっても大きく異なります。また、初動を間違えることで、より大きなトラブルに発展することもあります。
不正競争防止法や秘密保持に関してお困りの方は、ひとりで抱え込まず弁護士にご相談ください。
⇒ 労働相談@名古屋の詳細を見る