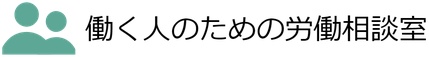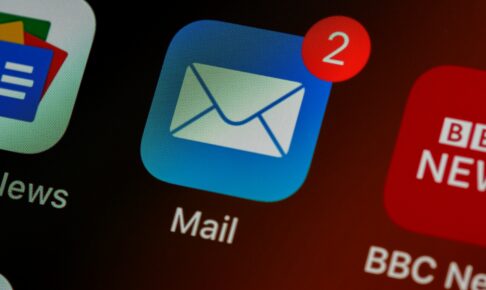病気や怪我で働けなくなるというのは、働く人にとっては大変深刻な問題です。この先、生活はどうなるのか、会社にいられるのか・・・など、心配の種は尽きません。
このように病気や怪我で働けなくなった場合、それが業務を原因とするものであれば、労災の休業補償給付を受けることができます。
業務とは無関係の原因で病気や怪我をした私傷病の場合と異なり、労災の場合には手厚い保護が受けられるのです。ここでは、そんな労災の休業補償給付についてみていきたいと思います。
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
詳しく見る
労災の休業補償給付とは
労災の休業補償給付とは、労働者が業務上怪我をしたり病気になった場合に、労災保険により受けられる給付の一つです。
怪我や病気の治療のために働けず、給料の支払いを受けられない期間について、その間の生活を補償するものとして支払われます。
もともと、労働基準法では、労働者が業務上、怪我をしたり、病気になり、その治療のために働けない場合について、使用者は、その期間中、平均賃金の6割の休業補償を行わなければならないと定められています(労働基準法第76条)。
労働者が、業務上、怪我をしたり病気になった場合に、その負担を労働者が負うといのは公平ではないことから、このような規定が設けられているのです。使用者の義務としては、このほかに、治療費の負担や後遺症が残った場合の障害補償、死亡した場合の遺族補償などが定められています。
そして、このような使用者による補償を万全なものとするものとして、労災保険制度が設けられています。
使用者が保険料の全額を負担する保険制度により、労働者が業務上、怪我をしたり、病気になった場合に各種の給付が行われるのです。
業務上とは何か~労災と私傷病の区別
労災の休業補償給付を受けるためには、その病気や怪我が「業務上」生じたものであることが必要となります。
業務上とは、要するに業務が原因となったという意味で(これを「業務起因性」といいます)、その前提として、労働者が労働関係のもとにあった場合に生じたものであることが必要です(これを「業務遂行性」といいます)。
どのような場合に、業務起因性や業務遂行性が認められるのか、というのは実は大変難しい問題が含まれています。
作業員が、使用者の指揮監督のもとで作業している最中に、足を踏み外して高所から転落し怪我をしたというような典型的なケースであれば、「業務上」であることは分かりやすいのですが、線引きが微妙なケースというのはたくさんあります。
例えば、飲み会・忘年会などの会社の行事に参加して事故にあった場合はどうか、勤務中に同僚と喧嘩して怪我をした場合はどうかなど、裁判でもいろいろな事例が争われています。
▼飲み会・忘年会での事故は労災になるのか
▼勤務中の喧嘩で怪我・死亡した場合に労災になるのか
また、近年、大変大きな問題となっているのは精神疾患のケースです。
「上司のパワハラによって鬱になった」「過労で鬱になった」等の主張がされるケースで、業務上の病気といえるどうかの線引きが問題になります。
この点については、認定を迅速に行うことができるように、厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、これに基づいた判断がされます。
▼精神障害の労災認定
休業補償給付の内容と平均賃金
では、労災の休業補償給付として、具体的に何が支給されるのでしょうか。
まず、平均賃金に相当する額(「給付基礎日額」といいます)の6割が「休業補償給付」として支給されます。
あわせて、平均賃金に相当する額(給付基礎日額)の2割が「休業特別支給金」として支給されます。
つまり、合計で平均賃金相当額の8割の支給を受けることができる事になります。
このように休業補償給付は、平均賃金をもとに算出されることになりますが、平均賃金とは、「これを算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額」(労働基準法12条)のことです。
「算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間」となっていますが、賃金締切日が設けられている場合には直前の締切日から起算します。
また、働き出してから3ヶ月も経過していないという場合には、雇い入れ後の賃金総額を雇い入れ後の期間の総日数で割って計算します。
注意したい点の一つは、「総日数」で割るという点です。つまり、休日も含め日数を数える必要があります。
また、「賃金総額」には、残業代はもちろんのこと、通勤手当、精皆勤手当等も含まれますが、年2回支給されるような賞与は含まれません。
休業補償給付を受け取れる期間
労災保険の休業補償給付は、休業4日目から支給されます。
つまり、休業を開始してから3日間は労災保険ではカバーされないことになります。
ただし、最初に見たとおり、労働基準法は、もともと使用者の休業補償義務を定めていますので、労災保険でカバーされない3日分については、直接使用者に対して休業補償(平均賃金の6割の支払い)を請求することができます。
問題は、いつまで休業補償給付を受け取ることができるか、ですが、この点については、上限が定められているわけではなく、休業補償給付の受給要件(①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため②労働することができないため③賃金をうけていない)を満たす限りは、その期間中は受給できます。
ただし、療養を開始してから1年6ヶ月が経過しても治っておらず、その障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当する場合には、休業補償給付に代えて傷病補償年金が支給されるようになります(労災保険法第12条の8第3項)。この傷病補償年金も、傷病等級に該当する状態が継続している間は、支給が続くことになります。
また、労働者が休業補償給付を受けている間に退職する場合もありますが、この場合も休業補償給付は引き続き支給されます。
労災保険法は「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」ことを明確に定めています(労災保険法12条の5)。したがって、退職をしても休業補償は従前通りもらえますし、金額ももちろん変わりません。
これは定年退職をする場合でも同じですし、期間満了で退職する場合も同じです。
休業補償給付の請求手続き
多くの場合は、会社が労災の請求手続きを行ってくれますが、会社が何もしてくれないという場合は、自分で請求手続きをとる必要があります。
請求書は労働基準監督署で入手できますし、厚生労働省のサイトからもダウンロードできます。
各種の請求ごとに用紙が異なるので、少し分かりづらいですが、休業補償給付であれば、様式8号を使うことになります。どの用紙を使えば良いか分からない場合や、記入の仕方が分からない場合には、労働基準監督署に問い合わせれば教えてもらえます。
請求にあたっては、会社に事業主証明を書いてもらう必要がありますので、必要事項を記入した用紙を渡して会社に事業主証明を書いてもらうように求めます。
会社が、労災とは認めないなどと言って協力してくれない場合もありますが、この場合は、事業主証明を求めたものの拒否された事情を説明した上で、事業主証明欄は未記入のまま、労働基準監督署に提出すれば足ります。
労災かどうかは、最終的には労働基準監督署が調査の上、判断することになります。
労災の休業補償給付と時効
労災の休業補償給付を請求する権利は、治療のために休業した日ごとに発生します。その日ごとに翌日から2年が経過すると時効によって請求することが出来なくなりますので、注意が必要です。
パート・アルバイトと労災の休業補償給付
ここまで説明してきた労災の休業補償給付については、パートやアルバイトの方についても、同じように適用されます。「パートだから」「アルバイトだから」という理由で、支給を受けられなくなることはありません。