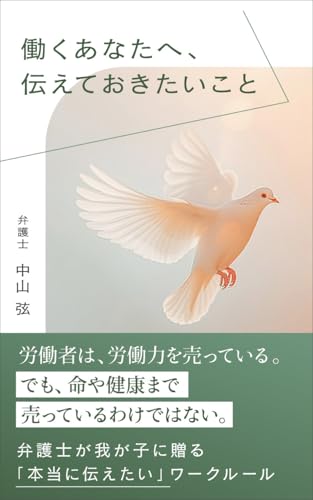円満ではない退職をする場合によく問題となるのが、退職金の支払いを巡るトラブルです。
解雇や懲戒解雇に伴って退職金の不払いや減額が制裁として使われたり、あるいはその可能性が、退職前のやりとりの中で交渉の材料に使われたりする場合もあります。
働いていた期間が長く退職金の金額も大きくなるほど、退職金の不払いや減額によるダメージも大きく、深刻な問題となります。
ここでは、そんな解雇や懲戒解雇時の退職金の不支給や減額の問題について解説していきます。
退職金請求権がそもそもあるか
そもそも退職金はどのような場合に請求できるかですが、退職金は退職にあたって当然に発生するというものではありません。
退職金を請求できるためには、就業規則や雇用契約などの何らかの根拠があることが必要です。
もっとも、退職金を請求するためには、就業規則や雇用契約に明確な定めがなければいけないというわけではありません。
一定の基準にしたがって退職金が支払われる慣行があるという場合も、退職金を支払うことが雇用契約の内容になっていると考えられますので、これに基づいて退職金の請求をすることが可能です。
求人票には退職金があると記載されていたのに、実際にはなかったというようなケースもありますが、そんなケースについてはこちらを参考にしてください。
⇒求人票と違う!給料や退職金は払ってもらえるか。
退職金の不支給、減額は許されるか
退職金の不支給あるいは減額が認められるためには、原則として就業規則等で不払いや減額について明記されている必要があります。
もっとも、退職金には「賃金の後払い」という性格もあり、これを懲戒解雇等によって当然に失うというのは相当ではありません。
そのため、たとえ、不支給や減額について明記されているとしても、これに基づいて当然に不支給あるいは減額ができるというわけではなく、実際に不支給あるいは減額するためには、労働者に永年の勤労の功労を抹消あるいは減殺してしまうほどの不信行為があることが必要です。
「永年の勤労の功労を抹消あるいは減殺してしまうほどの不信行為」かどうかは、背信性の程度や損害の程度、在職中の勤務状況等を考慮して判断することになります。
懲戒解雇時の退職金不支給
例えば、懲戒解雇がなされた場合に退職金は支給しないという就業規則に基づく退職金の不支給が争われた裁判例として平成20年5月19日札幌地裁判決をみてみます。
この事案は、旅行会社で35年間勤務し、営業所長の地位にあった原告が出張旅費の不正受給を繰り返したという理由で懲戒解雇され、「懲戒解雇された者には退職金は支給しない」という就業規則に基づいて退職金が不支給とされたというケースです。
賃金の後払い的性格
この事案で裁判所は、退職金には「功労報償的性質」と「賃金の後払い的性質」があるとしたうえで、この会社では、退職金を算定する際に、実際の勤務期間を月単位で把握した上で勤務点、役割成果点が付けられ、これが累積していくという方式をとっていることから、「賃金の後払い的性質が相当に強い」と指摘しました。
そして、このような場合には、従業員からすれば、退職金の受給を見込んで生活設計を立てるなどしているのであるから、そのような期待をはく奪するには、相当の合理的理由が必要となるとして、退職金全額を不支給とするには、
「当該労働者の永年の勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な不信行為が必要」
であるし、それに至らない場合には、
「解雇事由の内容、損害の程度、解雇に至った経緯、労働者の過去の勤務態度等,在職中の諸事情を考慮して合理性を有する範囲についてのみ,退職手当の一部を不支給とすることができるにとどまる」
と述べました。
重大な不信行為の有無
その上で、このケースでは
- 原告は営業所長の地位にありながら、15回にわたって22万6500円の出張旅費の着服を行っているのだから、その責任は重い
- 宿泊料として22万8000円を不正受給している上に調査の過程でも事実関係を積極的に明らかにしなかったという態度は芳しくない
- 着服金額は必ずしも高額ではなく、また既に返還していること
- 着服した金員を遊興費として使った証拠はなく、むしろ、一部について業務の延長ともいえる飲食で用いられたと伺われること
- 勤続35年であり、懲罰歴もなく、相応の功績を残してきたこと
としながらも、他方で
などの事情を挙げ、そうすると原告には、35年間の勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な不信行為があるとまではいえず、退職金の不支給条項は退職金の7割を不支給とする限度でのみ合理性がある(つまり3割だけは退職金を支払うべきである)という判断を下しました。
具体的にどのような場合に「永年の勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な不信行為」があった言えるのかという判断は大変難しい問題で、このケースでもなぜ「7割」不支給なら合理的なのかというのはなかなか説明しがたいのですが、裁判所の一つの感覚を知るという意味で参考になる事例です。
刑事処分を受けた後の懲戒解雇と退職金の不支給
懲戒解雇と退職金の不支給について判断した例として、もう一つ、平成25年12月11日東京高裁判決も紹介します。
この事案は、労働組合からの脱退を強要したなどとして強要罪により執行猶予付きの懲役刑判決を受けた労働者に対して行われた懲戒解雇の有効性が争われた事案です。
懲戒解雇が有効と判断されたため、併せて懲戒解雇処分を受けた場合に退職金を支給しないとする就業規則の規定に従って退職金を全額不支給とすることが許されるかが問題となりました。
結論として、裁判所は、懲戒解雇の場合に退職金を全額不支給とする就業規則の規定について、これが適用される場合は一定の場合に限定されるとしましたが、当該ケースにおいては退職金を全額不支給とすることが許されるとしました。
退職手当の性質
裁判所は、まずこの会社の退職手当については
賃金の後払いとしての性格と、功労報酬としての性格のうち、功労報酬としての性格が強い
としました。
(功労報酬としての性格を示すものとして、諭旨解雇の場合に退職金を2割減額する規定や、懲戒解雇の場合に全額不支給とする規定があること、定年前退職における特別昇給・特別加算金の規定があることが挙げられています。)
この点は、最初に紹介した札幌地裁の例で、当該会社の退職金について「賃金の後払い的性質が相当に強い」と指摘されているのと対照的です。要は会社の規定内容毎に、両者の性格のいずれが強いのかという点は異なってくるのです。
不払い規定が適用される場合
その上で、裁判所は、退職手当全部不支給の規定について
当該労働者の行為を理由にその全部を支給しないとすることが合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その全部を支給しないとすることは許されず、その事情に相当する一部を支給しないことができるにとどまる
としました。
その判断をするにあたって考慮すべき事情も詳しく述べられています。
まず、①基本的な考慮事情として
当該懲戒解雇に係る労働者の行為の性質、態様、非違の程度及びその結果(被害の内容、程度、使用者の会社に及ぼす影響・支障・損失の有無・程度、社会的影響の有無・程度等)、その経緯
が挙げられています。
特に、②使用者企業秩序等の維持の観点から考慮すべき事情として、
使用者の業務ないし会社施設の内外、当該労働者の行為の職務関連性の有無・程度等の事情
が指摘されています。
また,③当該労働者の行為が犯罪に該当する場合に考慮すべき事情としては
その犯罪の罪質及び罪責の軽重並びに当該労働者に対する起訴・不起訴処分の別及び有罪判決が言い渡された場合の処断刑の種類・軽重等、当該非違後における当該労働者の言動
が挙げられています。
当該ケースではどうなるか?
裁判所は、上に挙げたような要素を踏まえた上で、この事案では、
- ・職場秩序を甚だ乱す行為であったこと
- ・広く社会的に報道され会社の社会的評価を毀損するおそれも生じていること
- ・結果の重大さや行為態様の悪質さ
- ・被違行為後に反省の態度を全く示していないこと等
を指摘した上で、功労報酬的な性格が強く定められていると認められる退職手当の全部を支給しないとすることも許されると判断したのです。
他の具体例もさらに知りたいという方は、以下の記事を参考にして下さい。
⇒痴漢行為で懲戒解雇|退職金全額不支給は有効?東京高裁の判断
⇒出張旅費の不正受給で懲戒解雇|退職金全額不支給も有効とされた裁判例
また、自主退職し、退職金が支払われた後になって、懲戒解雇事由が発覚したとして退職金の返還請求がされるようなケースもあります。このような例については次の記事で解説しています。
⇒懲戒解雇事由の発覚と退職金の返還請求
不当な解雇や退職金を巡ってお困りの方へ
退職金不支給や減額に対してどう対応すべきかは、具体的な事情によっても変わってきます。ご自身の状況に照らして、今何をすべきかを知りたい方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
⇒労働相談@名古屋の詳細を見てみる
次に読むと理解が深まる記事
- そもそも解雇が無効であれば、当然退職金の不支給や減額は許されません。懲戒解雇の有効性の判断基準については、こちら。
⇒懲戒解雇されそうなときに知っておきたい法律知識と今すぐできる対処法 - 再就職の問題や失業保険に関しては、こちらで解説しています。
⇒解雇・懲戒解雇のデメリットとは?|再就職・退職金・失業保険への影響を解説 - 不当な解雇をされたときに知っておきたいポイントを体系的に整理した総合ガイドです。
⇒不当解雇トラブル完全ガイド|判断基準・対処法・相談先まとめ