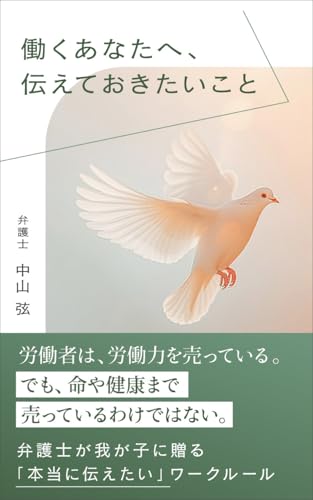競業避止義務と代償措置
退職後の競業避止義務を定めた合意は、労働者の職業選択の自由を不当に害さない限度でのみ有効となります。
その判断にあたっての重要な考慮要素として、職業選択の自由を制限することに対する代償措置があったかという点があります。
※競業避止義務の全体的な仕組みや判断基準を整理したい方は、まずこちらをご覧ください:
⇒ 退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?
例えば、競業避止義務を課される労働者について退職金の上乗せをする等がされている場合には、合意を有効とする要素として働きます。実際に、そのようなケースで競業避止の合意が有効と認められた裁判例もあります(競業避止の誓約書が有効と認められた裁判例)。
裁判例の中には、代償措置がなくても合意を有効としている例もありますが、いずれの事例も競業行為への制限が相当小さい点が着目されます。
顧客収奪行為の制限
たとえば、清掃用品等のレンタル及び販売等を行う株式会社が、元従業員に対して、競業避止義務違反に違反して顧客を奪った等として損害賠償を求めた事案(東京地裁平成14年8月30日判決)を見てみます。
この事案で、元従業員は、在職中に会社に対して、退職後、2年間は、「在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)並びにその隣接地域(都道府県)に在する同業他社(支店,営業所を含む)に就職をして、あるいは同地域にて同業の事業を起して、貴社の顧客に対して営業活動を行ったり,代替したりしないこと」と記載された誓約書を提出していました。
裁判所は、退職後の競業避止義務は、
期間、区域、職種、使用者の利益の程度、労働者の不利益の程度、労働者への代償の有無等の諸般の事情を総合して合理的な制限の範囲にとどまっていると認められるときは、その限りで,公序良俗に反せず無効とはいえない
とした上で、各要素について次のように指摘しています。
- 期間は退職後2年間と比較的短い
- 区域は、在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)並びにその隣接地域(都道府県)に在する同業他社(支店,営業所を含む)と限定されている
- 禁じられる職種は、マット・モップ類のレンタル事業で、契約獲得・継続のための労力・資本投下が不可欠であり、大手一社が市場を支配しているため新規開拓には相応の費用を要するという事情がある
- 会社は既存顧客の維持という利益がある一方で、元従業員に禁じられているのは顧客収奪行為に限られており、マット・モップ類のレンタル事業の市場・顧客層が狭く限定されているともいえないから、誓約書の定める競業避止義務を負担することで、マット・モップ類のレンタル事業を営むことが困難になるというわけでもない
- 上記事情に照らすと、職業選択・営業の自由を制限する程度はかなり小さいといえ、代償措置が講じられていないことのみで本件誓約書の定める競業避止義務の合理性が失われるということにはならない
そして、代償措置が講じられていない点については
としました。
そして、以上を総合すると、本件誓約書は公序良俗に反せず無効とはいえないと結論づけています。
裁判所も指摘しているように、本件誓約書が禁じているのは、会社の顧客の収奪行為のみで、会社の顧客以外の者に対しては、在職時に担当していたことのある営業地域で営業活動をすることも禁じられておらず、制約の程度は小さいという点が着目されます。
逆に制約の程度が大きい場合に、代償的措置が不十分であることを理由に競業避止義務の効力が否定された例:
⇒【裁判例解説】就業規則による競業避止義務は有効?退職金不支給が否定された裁判例
学習塾の講師の競業避止義務
もう一つ、代償措置のない競業避止義務の特約を有効と認めた例として、大阪地裁平成27年3月12日判決も見てみます。
この事案は、学習塾を経営する会社を退職後、近隣で学習塾の営業を始めた元講師に対して、営業の差止めや損害賠償請求等が行われたケースです。
この会社の就業規則では、退職後2年間は、担当していた教室から半径2キロメートル以内で自塾を開設することを禁じる旨が定められていました。
裁判所は、このような就業規則の規定は、投下資本の回収の機会を保護するための合理的なものであって、合理的な範囲で退職後の競業を禁止することは許されるとした上で、次のような点を指摘して本件規定は合理的な範囲であると判断しています。
- 退職後2年間に限定していること
- 指導を担当していた教室から半径2キロメートル以内の限度で、自塾を開設することのみを禁ずるものであること
- 上記の圏外で開業することは禁じられておらず、上記圏内であっても競合他社に勤務することは禁じられていないこと
- 退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?
競業避止義務の基本的な仕組みや、誓約書の有効性の判断基準をわかりやすく整理した解説記事です。 - 「競業避止義務に違反している」と言われたときの正しい対応法
元の会社から通知を受けた場合に慌てずにとるべき対応ステップを詳しく解説しています。 - 退職・転職で気をつけたい競業避止義務と秘密保持義務【まとめ】
競業避止義務・秘密保持義務全般について、さらに詳しく知りたいという方はまとめ記事からご覧ください。
そして、代償措置が講じられていない点についても、上記を考慮すると、合理性の判断には影響を及ぼすことはないとしました。
最初に紹介した東京地裁の例と同じく、退職後の競業行為に対する制約の程度がかなり限定されているということが着目されます。
一方で、職業選択の自由に対する制約が大きい場合には、代替措置の不存在などを理由に、競業避止義務の効力が否定されたり、その意味内容が限定されることがあります。
⇒競業避止義務違反で退職金を返せと言われたら?返還請求が否定された裁判例を弁護士が解説
次に読むと理解が深まる記事
競業避止義務でお悩みの方へ
競業避止義務の効力は、具体的な事情によって結論が大きく変わります。 「自分のケースはどう評価されるのか」「損害賠償を請求されるのではないか」と不安な方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
⇒労働相談@名古屋の詳細を見る