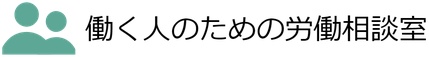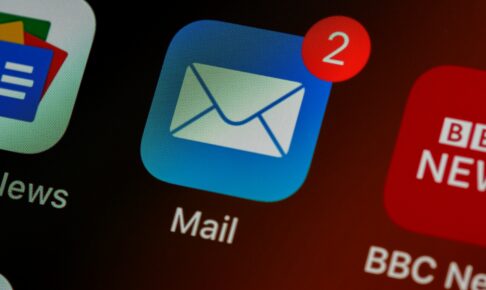「辞めたいのに会社が辞めさせてくれない」「勝手に辞めたら損害賠償だと脅された」──そんな悩みを抱えていませんか?
労働者には「退職の自由」があり、会社の同意がなくても辞めることは可能です。
本記事では、会社からの引き止めに法的にどう対処すべきか、そして退職するための正しい手順を、法的観点からわかりやすく解説します。
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
詳しく見る
一方的に辞められるか~退職の自由
労働者が会社を辞めることについて会社の側も特段文句を言わないというのであれば良いのですが、問題は、労働者の側が「仕事を辞めたい!」と言っているのに、会社がこれを認めないという場合です。
このような場合に、会社が了承しないまま一方的に辞めることは法的に可能なのか?というのが最初の大きな問題です。
この点については、雇用契約の期間が決まっている場合と、決まっていない場合とで事情が違ってきますので、場合を分けて説明します。
雇用期間の定めがない場合
雇用期間の定めがない場合は、働く人が「辞めたい」ということを会社に伝えてから2週間が経過すると雇用契約は終了します。
具体的には、民法627条1項が次のように定めています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、雇用期間の定めがない場合は、契約を終わらせたい日の2週間以上前に、「辞めます」ということを会社に伝えれば、会社が了承しなくても法律的には問題なく辞められるのです。
ポイントは、後で説明する「雇用期間の定めがある場合」と違って、どのような理由であれ辞められるという点です。
もっとも、会社によっては、就業規則や雇用契約書の中で予告すべき期間を2週間より長く定めている場合があります。
このような規定は、必要以上に働く人を拘束するものですので、法律的に有効と認められるか疑問はありますが(特に予告期間があまりに長すぎるという場合)、学説上も争いはあるところですので、「無難に辞めたい」というのであれば、その決められた予告期間にしたがって、事前に辞めることを会社に伝えた上で辞めることになります。
また、遅刻や欠勤があっても賃金控除がされない純然たる月給制の場合には、次のとおり、次期以降に対してのみ、しかも当期の前半にその予告をすることが必要とされています。したがって、このような月給制の方の場合は、賃金計算期間の前半に申し出ることが必要になります。
(民法627条2項)
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
同じく、遅刻や欠勤があっても賃金控除がされない純然たる年俸制の場合には、3ヶ月前に申し出ることが必要とされています。
(民法627条3項)
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
雇用契約の期間が定まっている場合(1年以内の場合)
これに対し、雇用契約の期間が定まっている場合(1年以内の場合)は、労働者は「やむを得ない事由」がある場合に、会社の了承を得なくても、会社を辞めることができます。
具体的には民法628条が次のように定めています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
では、どのような場合に「やむを得ない事由」があると言えるのでしょうか。
たとえば、働き始めてみたら、労働条件が働く前に言われていたものと全然違う!というような場合や、体を壊すような長時間労働が続いているような場合には、やむを得ない事由があるといえるでしょう。
こうした「聞いていた労働条件と違う」というケースについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
▼求人票と違う!給料や退職金は払ってもらえるか。
契約期間が1年を超える場合
さて、上に書いたのが、雇用期間があらかじめ決まっている場合についての原則的なルールですが、例外として、雇用契約の期間が1年を超える場合には、事情が違ってきます。
この場合は、次のとおり、契約期間の最初の日から1年が経過すれば、いつでも一方的に、つまり会社の了承を得ずに退職することができるとされています。
(労働基準法137条)
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者は(略)民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、高度専門的知識等を有する方や60歳以上の方は除かれています。
専門的知識等を有する方とは、例えば以下のような方です。
・博士の学位を有する者
・公認会計士や医師
・特許発明者
こういった例外にあたらない限りは、契約期間があらかじめ定まっていても、それが1年を超えているという場合は、1年が経過すればいつでも、自由に辞めることができるのです。
辞める時の具体的な手続き
次に、実際に、辞める意思があることを会社に伝える方法についてです。
口頭で伝えてももちろん構わないのですが、後々トラブルになるのを防ぐためにも、書面の形で会社に提出しましょう。
書面には、提出する日付と氏名を記載し、「×月×日をもって退職致します」と明記します。(なお、退職届と退職願の違いについてはこちら≫退職届と退職願は何が違うか)
その際、どのようなものを提出したのかが後に分かるようにするためにコピーを手元に残しておくことも大事です。
また、本格的にトラブルになる恐れがあるという場合には、内容証明郵便で会社に送り、会社を辞める意思を伝えたこと、その時期について後々証明できるようにしておくというのが一番確実な方法です。
会社によっては、些細な業務上のミスを理由に「退職したらこの損害賠償請求をする」などといって脅しにかかる場合がありますが、こうした会社からの損害賠償請求の問題については、以下の記事で詳しく説明していますのでご覧ください。
▼仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか
辞めるとお金を請求される!?
退職をためらうケースの一つとして、会社を辞めると何らかの制裁的な金銭の支払いをしなければならない旨の合意がされている場合があります。
例えば、退職した場合には、在職中に受けてきた研修費用を遡って支払わなければならない、と雇用契約上定められているような場合です。
これに関連して、知っておきたい法律上の大原則は「違約金の定め及び損害賠償の予定の禁止」(労働基準法16条)です。
そもそも、労働者にはどの会社で働くかということを決める自由があります。
ところが、退職すると制裁として金銭の支払いをしなければいけないということになると働く人は辞めたくても辞められないということになってしまいます。
そこで、労働基準法16条は、
『労働者が雇用契約にしたがって働かないという場合(会社を途中で辞めるという場合もそのひとつです)について、たとえ一定の金銭を支払うことをあらかじめ約束していたとしても、その効力は認められない』
と定めているのです。
このように働く人の退職の自由を守るために、「違約金の定め及び損害賠償の予定の禁止」というルールが定められていることから、退職をした場合に例えば研修費用を返還するというような合意も、その合意が「労働者の退職の自由を奪っている」と評価される場合は、法的には無効ということになります。
問題はどのような場合に「労働者の退職の自由を奪っている」と評価されるかですが、裁判例では、例えば研修費用の場合であれば、
- その研修を受けるか否かを労働者が自由に選べたか
- 研修内容の業務との関係性
- 拘束期間の長さや拘束の程度
等を総合的に考慮して判断されることになります。
▼解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか~
▼退職勧奨(退職勧告)が違法となるとき)
退職を巡ってお困りの方は、お気軽にご相談ください。
▼名古屋の弁護士による労働相談のご案内