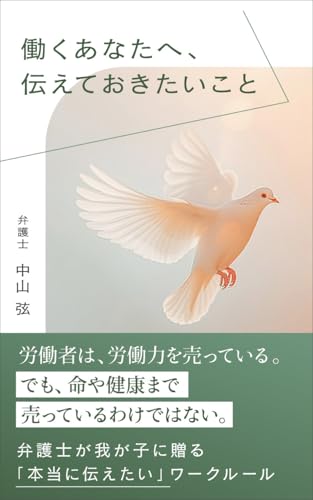「前職の取引先から、“うちに来ない?”と誘われて転職したけど、元の会社に責められないか不安…」
「取引先への転職は法的に問題ないのだろうか」
退職後に、以前の勤務先と関係のあった取引先企業に転職するケースは少なくありません。お互いに顔も仕事も分かっていて、スムーズに働けるのはメリットですが、一方で「元の会社とのトラブルにならないか?」と不安を感じる方もいると思います。
確かに、このような転職には、競業避止義務や秘密保持義務との関係でトラブルとなりうるケースがあり、注意が必要です。
本記事では、退職後に取引先に転職することの法的問題点と、リスクを避けるために確認しておくべきポイントについて解説します。
退職後に取引先へ転職するのは違法なのか?
まず大前提として、労働者には「職業選択の自由」がありますので、退職後に取引先企業に転職すること自体が直ちに違法となるわけではありません。
ただ、次のようなケースでは、元の会社との間でトラブルに発展する可能性があります。
・元の会社と取引先企業とが競業関係にあり、在職中に退職後の競業避止義務に関する誓約書にサインしていたり、就業規則に定めがある場合
・在職中に退職後の秘密保持義務に関する誓約書にサインしていたり、就業規則に定めがある場合
・元の会社と取引先企業との間の契約上、採用や引き抜きが制限されていた場合
・在職中から、転職予定の取引先企業のために、元の会社の利益を害する行為をしていた場合
こうしたケースでは、場合によっては転職先企業も巻き込んだ形で、損害賠償などの紛争が生じることがあるのです。
取引先に転職することによって生じうるリスク
以上のように、取引先への転職は一定の条件下ではトラブルにつながるリスクがあります。
ここでは、その代表的な法的リスクについてもう少し詳しく見ていきましょう。
競業避止義務の問題
労働者は、在職中、使用者と競業する行為によって使用者に不利益を与えてはならないという「競業避止義務」を負っています。
一方、退職後は、雇用関係が終了している以上、本来であれば、このような競業避止義務は負わないのが原則です。
しかし、多くの会社では、就業規則で退職後の競業避止義務について定めたり、入社時あるいは退職時に、退職後の競業他社への就職を制限する誓約書を書かせています。
そのため、取引先が元の会社と競業関係にある場合には、この競業避止義務に反していないかが大きな問題となるのです。
秘密保持と不正競争防止法
不正競争防止法との関係
取引先に転職する場合には、元の会社に在籍していた当時知った情報が、そのまま転職先で使われうることになり、情報の性質、取引の内容によっては、大変大きな影響を与えることになります。
そのため、元の会社と転職する取引先とが競業関係にあるか否かにかかわらず、秘密保持の問題も大きな問題となります。
この関係で知っておきたいのは、不正競争防止法という法律です。
不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争を確保する」ことを目的として、特定の不正な行為に対して差止請求や損害賠償を認めている法律ですが、その中で営業秘密の不正な開示行為も定められています。
そのため、不正な開示行為に該当する行為が行われると、不正競争防止法違反として、損害賠償請求などの責任追及の根拠とされることがあるのです。
行為の態様によっては、刑事罰も定められています。
もっとも、不正競争防止法で保護される「営業秘密」はかなり厳格に定められています。
どのような情報が営業秘密に該当するのかについては、不正競争防止法における「営業秘密」とは?裁判例にみる秘密管理性のポイントをご覧ください。
就業規則・誓約書による秘密保持義務
これとは別に、退職後の秘密保持義務についても、就業規則に定めがあったり、入社時あるいは退職時に誓約書を作成している場合が少なくありません。
そのため、取引先に転職する場合には、これらの秘密保持義務違反が生じないかも注意する必要があります。
従業員引き抜きに関する問題
元の会社と取引先との関係によっては、会社間に従業員の引き抜きを一定制約する合意がある場合もあります。
また、大量引き抜きなどの特殊なケースではありますが、従業員の引き抜き自体が違法性を持つという場合もありえます。(詳しくは、従業員の引き抜き行為が違法となる場合とは)
これらは、元の会社と転職先の取引先との間という、もっぱら会社間の問題ですが、そこに巻き込まれるという意味において一定のリスクがあります。
リスクを避けるために確認しておくべきポイント
ここまで見てきたように、取引先への転職は、状況次第では思わぬトラブルに発展することもあります。
そのため、取引先への転職を検討する際には、次の点をしっかり確認しておくことが大切です。
1. 就業規則や誓約書の内容を確認する
まず、会社の就業規則をよく読んで、退職後の競業行為や秘密保持についてどのような定めが置かれているかを確認しましょう。
入社時などに競業行為や秘密保持に関する誓約書を書いたという場合には、その文面もよく確認しましょう。
2. 就業規則や誓約書の効力を見極める
就業規則や誓約書で禁止された行為に文言上明らかに当てはまらないという場合は良いのですが、形式的には当てはまってしまうという場合には、その効力を見極める必要があります。
実は、競業避止義務や秘密保持義務に関する就業規則の定めや合意は、退職者の「職業選択の自由」を制約するものであることから、どのような内容でも効力が認められるわけではありません。
一定の場合には無効となったり、その内容が限定的に解釈されたりします。(詳しくは、退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?をご覧ください)
したがって、就業規則や誓約書に果たしてその文言どおりの効力があるのかについて見極めていく必要があります。
もっとも、競業避止義務や秘密保持義務を定める条項の有効性は様々な事情に基づいて判断されることから、見極めるといっても容易なことではありません。
少しでも不安がある場合は、軽視せずに、専門家である弁護士の判断を仰ぐことが重要となります。
3. 退職時の誓約書に不用意に署名しない
退職前で、これから誓約書への署名を求められるという場合には、不用意に署名せず、その対処の仕方について検討することが大切です。
重要なのは、誓約書に署名しなければならない義務が労働者にあるわけではないという点です。
誓約書への署名を求められた時の対応については、次の記事で解説しています。
⇒退職時に誓約書へのサインを求められたら?断り方と注意点を弁護士が解説
4. 在職中の行動の注意点を知る
在職中は、使用者の利益を不当に侵害してはならないという「誠実義務」を負っています。
これに対して退職後はそのような義務を負わないことから、在職中の行為か退職後の行為かという区別は非常に大きな意味を持ちます。
転職先が取引先企業である場合、在職中から接触する機会も多いことから、在職中の行為として何が許されるのかについて、より正確に理解しておく必要があります。
在職の行為として何が許されるかについて詳しくは、在職中の転職活動や競業準備は違法?裁判例でみる誠実義務違反をご覧ください。
5. 内容証明などの警告が届いた場合はすぐに相談を
もし退職後に元の会社から「競業避止義務違反」「秘密保持義務違反」などの指摘を受けた場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
安易に自己判断で対応すると、事態がより悪化していくこともあります。
正しい対応方法については、次の記事でも解説しています。
⇒「競業避止義務に違反している」と言われたら?元の会社から警告を受けたときの正しい対応法
まとめ
退職後に取引先へ転職すること自体は、何ら問題のある行為ではありませんが、これまで見てきたように、競業避止義務や秘密保持義務などとの関係で、状況によっては法的トラブルにつながる可能性があります。
トラブルを避けるためには、
・事前に就業規則・誓約書をよく確認する
・在職中の行動に注意する
・不安があれば弁護士に相談する
といった基本的な対策を徹底することが重要です。
競業避止や秘密保持の問題でお困りの方へ
競業避止や秘密保持トラブルに関する判断は、具体的な事情によっても大きく異なります。また、初動を間違えることで、より大きなトラブルに発展することもあります。
競業避止や秘密保持の問題でお悩みの方は、お一人で悩まず弁護士にご相談ください。
次に読むと理解が深まる記事
- 転職をした後の元の顧客との関係について悩まれる方は少なくありません。
⇒退職後に元の会社の顧客と取引する行為は許されるか - 退職時の顧客への挨拶に関して不安を感じているかたは、こちら。
⇒退職の挨拶と在職中の競業避止義務 - 競業避止や秘密保持についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事からご覧ください。
⇒退職・転職で気をつけたい競業避止義務と秘密保持義務【まとめ】