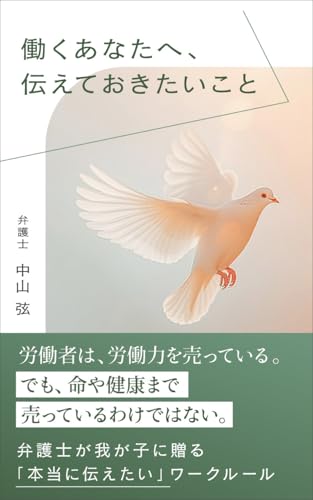「契約社員で『雇用期間の定めあり』って言われたけど、これってどういう意味?」「更新されると思っていたのに、突然契約終了ってアリ?」
そんな不安や疑問を感じていませんか?
雇用期間の定め方は、働く人の将来に大きく関わる重要なポイントです。この記事では、契約社員やパートの方向けに、次の内容をわかりやすく解説します。
「雇用期間の定めあり・なし」の違いとは?
契約の更新はどこまで可能?
突然の「雇い止め」は違法にならないの?
雇用契約を結ぶ前や更新時に知っておくべきポイントを、法律的な観点から説明します。
雇用期間とは?雇用期間の定めあり・なしの違い
雇用期間とは、労働契約が継続する期間のことです。
会社と結ぶ労働契約には、
・一定期間で契約が終わる「定めあり」
・特に期間を設けず働き続ける「定めなし」
の2種類があります。
このうち、雇用契約がいつ終了するかを決める場合に、その終了までの期間のことを雇用期間というのです。
雇用期間の上限
雇用期間の上限は原則として3年までです。
ただし、高度な専門的知識等を持つ労働者(例えば、公認会計士や医師など)や、満60歳以上の労働者については、例外的に5年までとされています。
雇用期間の定めと更新・雇い止め
雇用期間の定めがある契約の場合、期間が満了すれば契約は終了します。これが「期間の定めあり契約」の基本的な仕組みです。
しかし、現実には、こうした契約の多くが終了せずに「更新」され、実質的には長く働き続けることになります。
「更新」とは、本来期間満了によって労働契約が終了するところを、再び同様の条件で契約を結び直すことを指します。この“更新”が繰り返されることによって、契約社員やパートであっても「ずっと働けるだろう」と思っている方も少なくありません。
ところが、ある日突然「今回で契約終了です」と言われるとどうなるでしょうか? それがいわゆる雇い止めです。
契約の継続を当然に期待していた労働者からすれば、雇い止めは大きなショックであり、トラブルに発展することもあります。
雇い止めが許されない場合
雇用期間の定めがある契約の場合でも、例えば更新手続きが形骸化していたり、長期間にわたって更新が繰り返される等によって、実質的には「期間の定めのない契約」とほぼ変わらなくなっているような場合があります。
また、このような場合でなくても、契約が更新されることを労働者が期待してもやむを得ないと思えるような様々な事情がある場合もあります。
こうした場合には、期間の定めがある契約であっても、当然に期間満了によって契約が終了するわけではなく、合理的な理由や社会的相当性がなければ会社による雇い止めは許されないことになっています(労働契約法19条)。
具体的にどのような場合に、雇い止めが許され、また許されないのかについて、実際の裁判例を元にした詳しい解説をこちらの記事で行っていますのでご覧ください。
⇒雇止めの正当な理由とは?認められるケース/認められないケースを裁判例で解説
「雇用期間の定めあり」の契約を締結する際の注意点
このように雇い止めには一定の法律的な規制がありますが、それでも期間満了によって契約終了するのが原則という意味において、雇用期間の定めのある契約は、雇用期間の定めのない契約と比較すると地位の不安定さは否めません。
働き始める際には、この点をきちんと理解したうえで、更新の条件(原則更新なのか、どのような場合に更新され、あるいは更新されないのか)について事前にしっかり確認しておくことが大切です。
また、雇用期間の定めのある契約で働き始めた場合にも、一定期間働くことによって、期間の定めのない雇用契約に転換させることができます。このような無期転換については、次の記事で解説していますので、ご覧下さい。
⇒契約社員が無期雇用になるために何をすべきか
雇い止めでお困りの方へ
不当な雇い止めに対してどう対応すべきかは、個別具体的な事情によっても変わってきます。ご自身の状況に照らして、今何をすべきかを知りたい方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
⇒労働相談@名古屋の詳細を見る
次に読むと理解が深まる記事
- 雇い止めがどのような場合に許されるのかについて知りたい方は、こちらをご覧ください。
⇒雇止めの正当な理由とは?認められるケース/認められないケースを裁判例で解説 - 雇用期間の定めがある契約であっても、内容や実態によっては単なる“試用期間”とみなされるケースもあります。このようなケースについては次の記事で解説しています。
⇒雇用期間と試用期間~実質的には試用期間と評価される場合 - 不当解雇全般について詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事からご覧ください。
⇒不当解雇トラブル完全ガイド|判断基準・対処法・相談先まとめ